4.授業評価について
4.1.アンケート結果
登録者:277人、出席者:約70人(25.3%)、アンケート回答者:95人(34.3%)
講義回数: 26回(期末試験を除く)
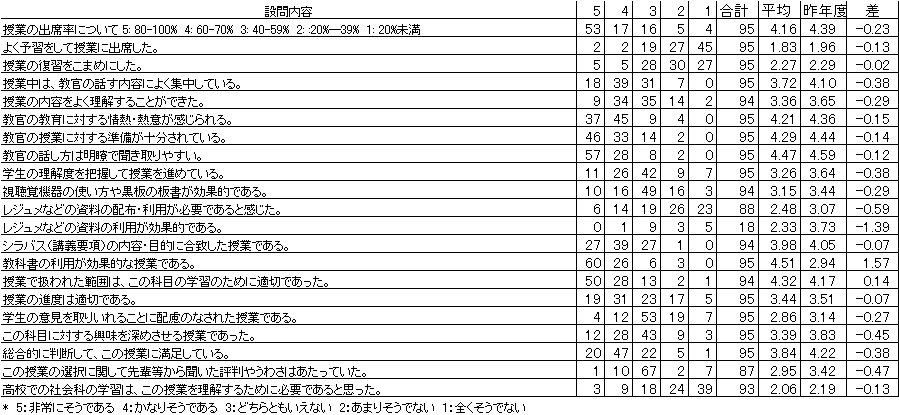
財産法総論(夜間主)
期末試験採点結果
採点基準
学生による授業評価
| 登録者数 | 提出者数 | 3点 | 2点 | 1点 | 0点 | 平均点 |
| 277人 | 193人 | 94人 | 81人 | 14人 | 4人 | 2.4点 |
レポートはこの講義中に全部で2回の提出を求めます。
レポートは、毎回1点から3点までの3段階評価です。提出されなかった場合は、0点とします。2度のレポートで、0点から6点になり、6点以上は優、5点以上は良、4点以上は可、3点以下は不可です。
4点以上の人は、期末試験を受けなくても、単位を認定します。
期末試験は、レポートの提出とは無関係に(レポートを一度も提出しなくても受験できます。レポートを二度提出しても有利にはなりません)、優・良・可・不可を認定します。
1.2.採点基準(* ドイツ語で出題したものについては、省略します。)
(1)様式に適っているか
400字詰原稿用紙(ワープロなどの場合も原稿用紙のマス目の形式にすること)5枚程度(±1)が遵守されているか
ワープロで文字数の記載のあるものは、減点しています。それ以外の様式違反は、提出されたものとしては取り扱っていません。したがって、0点です。
(2)文章表現が正確か
誤字脱字略字がないか
日本語の表現として正しいか
文章の構成が明瞭か(矛盾・重複などがないか)
(3)以下の事項が十分に明らかにされているか
(1)債権者主義の根拠
債権者主義を合理化する諸根拠が述べられているか
(2)債権者主義の問題点
債権者主義の根拠について検討されているか
債権者主義にしたがった場合に生じる不都合について述べられているか
(3)民法534条の妥当性についての検討
学説などにおける適用範囲を制限する努力について述べられているか
(4)レポート作成に際して参考にした文献
(4)自分の頭で考えようとしているか
自分の頭で考えようとしていることが読み取れるものについては、加点しています。
<コメント>
誤字(特に検「当」)・脱字・略字(権の字)、文法的な誤り(主語と述語の対応など)、初歩的な文章の書き方の誤り(段落のはじめは一字下げる、段落を適当に設けるなど)、文献の引用の仕方の不備(著者名・書名・出版社など)などが目立ちました。当然減点しましたが、次回のレポートや期末試験では十分に気をつけてください(就職試験などでも)。
内容としては、わずかな参考文献を基にして、それをほとんど写しただけのものが目立ちました。自分なりに考えて検討してもらうことを期待したのですが、やや期待はずれでした。債権者主義の問題点はどこにあるのか、学説がそれをどのように克服しようとしているのかが、ちゃんと理解できているとよいのですが・・・。
とはいえ、限られた範囲ではありますが、講義では十分に言及できない条文の沿革や学説の対立について、調べ・考えてもらう機会として、また、期末試験前のみならず学期途中にも勉強してもらう機会として、今回のレポートにはそれなりの成果があったと考えています。しかし、任意提出にもかかわらず、講義の出席者を大幅に上回る(2倍?)提出があったため採点には苦労しました。受講者が100人を超える場合には、レポートを複数回提出してもらうことは、教官側の負担という点から無理があると感じました(ほかの仕事もあって、今回だけでも胃が痛くなりました)。ただし、今回は、一旦はじめた以上、最後までやり通すため、もう一度レポートを提出してもらう予定です。
TOPに戻る↑
2.第2回レポート
2.1.採点結果
* 集計ミスが判明しましたので、一部修正しました(10/10)
| 登録者数 | 提出者数 | 3点 | 2点 | 1点 | 0点 | 平均点 |
| 277人 | 183人 | 95人 | 76人 | 2人 | 10人 | 2.4点 |
(2)文章表現が正確か
誤字脱字略字がないか
日本語の表現として正しいか
文章の構成が明瞭か(矛盾・重複などがないか)
段落の区切りがないもの、段落の書き始めを1字下げていないものも減点の対象です。
(3)以下の事項が十分に明らかにされているか
(1)民法上の法的手段が言及されているか
賃貸人への履行請求、占有訴権、妨害排除請求権の代位行使、賃借権に基づく妨害排除請求など
不法行為については加点しています。
(2)それぞれの問題点の検討が十分にされているか
直接的な解決ではないこと、占有が前提になっていること、転用であること、債権であることなど
第三者が新所有者である場合や二重賃貸借である場合についての言及は加点しています。
(3)参考文献が適切に示されているか
<コメント>
誤字(たとえば「見当」)・脱字・略字、文法的な誤り、初歩的な文章の書き方の誤り、文献の引用の仕方の不備など、相変わらずです。
また、わずかな参考文献を基にして、それをほとんど写しただけのものがやはり目立ちました。そのためか説明不足やレポート作成者自身が理解していないため意味不明になっているものもあります。債権者代位権で賃貸人の妨害排除請求権を代位行使と賃借権に基づく妨害排除請求権の行使とを同じことと理解している人がいます。また、債権者取消権の転用、債権者代位権の代理行使は、おかしくないでしょうか。さらに、闖入など意味を理解して使用しているのでしょうか。
レポート相互の間で類似しているのも、参考文献を転記しためだと思いますが、あまりに類似しているものについては減点しています。見落としがあるかもしれませんので、同じ内容なのに点数が違うという人は、申し出てください。
以上のようなことで読む気力が続かなかったため、返却が遅れました。「いつ返却してもらえるのか」「試験勉強すべきかどうかがわからないのは困る」と研究室を訪問した学生が複数いました。単位だけが欲しいということでしょうが、そのように主張することに何のためらいも感じられないことが、もはや驚きではない時代のようです。
大学審議会の平成10年10月26日の答申『21世紀の大学像と今後の改革方策について』に、「学期末の試験のみでなく学生の授業への出席状況、宿題への対応状況、レポート等の提出状況等、日常の学生の授業への取組と成果を考慮して多元的な基準を設定することが望ましい」(49頁)とありますが、200人以上の講義においてレポートを課すことは、現状では無理であることが判明しました。
なお、第二回レポートは事前の予告どおり講義中にしか返却しません(第一回のレポートは試験終了後に受け取ることを認めています)。最後の講義が終了した後、私の手元に残っているレポートの提出者は、期末試験を受験しても判定しないか「不可」にしかなりませんので、気をつけてください。
TOPに戻る↑
3.期末試験
3.1.期末試験結果
* 追試験該当者が出たため、一部変更しました(7/27)
* 集計ミスが判明しましたので、一部修正しました(10/10)
| 登録者数 | 受験者数 | 優 | 良 | 可 | 不可 |
| 278人 | 222人 | 59人 | 73人 | 57人 | 33人 |
第2問
故意・過失、責任能力、違法性、因果関係に言及し、その内容について説明されていること。
過失の客観化、相関関係説、成立における因果関係、範囲における因果関係、相当因果関係、立証責任などについての説明があること。
TOPに戻る↑
4.授業評価について
4.1.アンケート結果
登録者:277人、出席者:約70人(25.3%)、アンケート回答者:95人(34.3%)
講義回数: 26回(期末試験を除く)
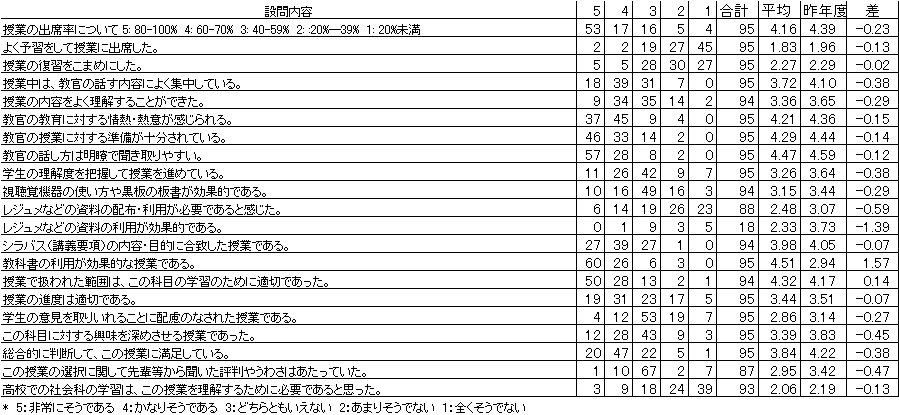
4.2.コメント
(1)出席率について
出席率がかなり悪いという印象です。レポートの提出で単位を認定したこと、出席率の悪い人の自由記載欄に「教科書と同じ内容である」という意見がありましたので、教科書に沿って講義したことなどが原因として考えられます。解りやすいようにと教科書に沿って講義したことが裏目に出たようです。
講義を受けたことを前提に、レポートや期末試験などが課されるわけですから、講義に出席してもらうように工夫する必要がありそうです。受験勉強の弊害だと思いますが、試験に合格しさえすれば、講義に出なくてもよいと考えている人が多いようです。
(2)予習・復習
予習・復習しやすいようにと考えたのですが、効果はありませんでした。自由記載欄に、「予習していっても講義で省略されるので、やる気がなくなる」旨の意見がありました。事前に省略部分をもっと具体的に示すべきであったと反省していますが、講義の進度との関係で省略部分を決定している面がありますので、もう少し工夫が必要なようです。
(3)集中している・理解することができた
これらの項目も、昨年より下がっているのは意外です。「集中」については、教科書に沿っているため講義する私の方も、少しやりにくかった点がありますので、それが影響しているのかもしれません。しかし、理解度まで下がっているのは、なぜでしょう?教科書を解説しているつもりなのですが・・・。もう少し思い切って内容を絞った方が良いのかもしれません。
(4)理解度の把握・学生の意見の取り入れ
こられは相変わらず課題として残っています。今年は、レポートを課したため、アンケートなどを行う余裕はありませんでした。200人以上の講義では、理解度の把握・意見の聴取というのは無理ではないかと思っています。
(5)教科書の利用
「教科書の利用が効果的である」と「授業で扱われた範囲が適切である」という項目は、昨年よりかなり良くなりました。教科書に沿って、教科書の解説を行ったのですから、当然ですが・・・。「教科書の利用が効果的である」の点数が良いことが、良い授業であるという評価になるのか、少し疑問を感じました。
(6)授業の進度
昨年とほぼ同じです。自由記載欄でも、授業の進度をもう少し遅くして欲しいという意見がかなりありました。私の性格の問題でもあるのだと思いますが、もう少し工夫したいと思います。
(7)授業評価全般について
昨年に比べて、ほとんどの項目で評価が下がっています。原因は、いまのところ不明です。
自由記載欄で見るかぎり、レポートは試験だけの一発勝負でないことや文献を調べ考える機会が与えられたことなどから、おおむね評判がよかったように思います。しかし、出席率低下の原因になったようですし、私の体力という点からも、これを200人以上の講義で継続することは無理であることが判明しました。
昨年よりも厳しい意見も特にありませんでした。
ただ、民法のほかの科目、特に債権法総論で講義されている部分を前提にして講義することは、科目の性格上やむを得ませんので、編入生などには少し難しかったかもしれません。
| 登録者数 | 受験者数 | 優 | 良 | 可 | 不可 |
| 36人 | 28人 | 25人 | 3人 | 0人 | 0人 |
TOPに戻る↑
2.授業評価について
2.1.アンケート結果
登録者数:36人 出席者数:約20人 アンケート回答者:15人
講義回数: 27回(期末試験を除く)
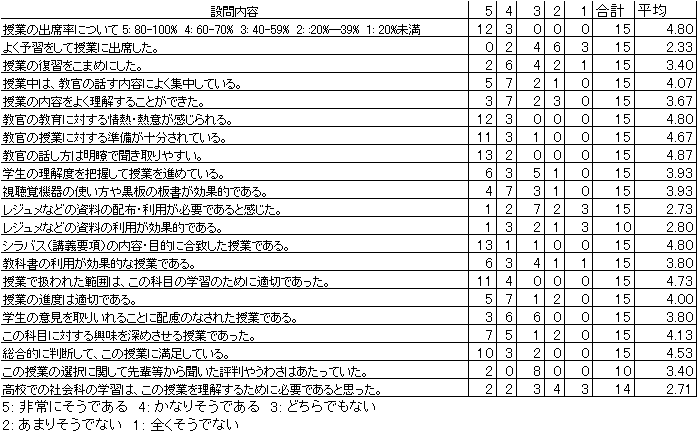
2.2.コメント
(1) 授業の復習
毎回、レポートを提出してもらったため、「復習した」の部分がかなり良くなっています。質問に「こまめ」とあることが、点数を少し低くしている原因かもしれません。
レポートは、社会人の方々にはかなり負担だったと思いますが、肯定的な評価が多かったので、安心しました。
(2)授業の内容の理解
「授業内容をよく理解することができた」、「レジュメなどの資料の配布・利用が必要であると感じた」、「授業の進度は適切である」の項目にはやや改善の余地があるようです。特に、夜間主コースは、2コマ連続の授業であるため、講義している方もかなり疲れます。解説の後に例題を解くなど、目先を変える工夫が必要かもしれません。
1.期末試験
1.1.採点結果
| 登録者数 | 受験者数 | 優 | 良 | 可 | 不可 | 平均点 |
| 64人 | 52人 | 17人 | 23人 | 8人 | 4人 | 75.1点 |
1.2.採点基準
問1
(1) 審級を異にする裁判所の審理を3回受けることを認める制度。上訴(控訴、上告)が認められる。
日本の裁判所が、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所からなること。
(2) 民事責任(例:治療費などの損害賠償)・刑事責任(例:業務上過失致傷)・行政訴訟(例:免許取消についての争い)
(3) 私法:私人間の法律関係を規律する法律。例:民法、商法。公法:国家の組織や公権力の行使を規律する法律。例:憲法、行政法、刑法、訴訟法。
(4) 裁判を行う基準となる法律。例:民法、刑法
(5) 裁判のやり方を定める法律。例:民事訴訟法、刑事訴訟法
(6) 民法
(7) 民事訴訟法
問2
債務不履行責任(民415条)と不法行為責任(民709)
債務不履行責任:(要件)債務不履行、債務者の帰責事由、債務不履行と損害との間の因果関係⇒(効果)損害賠償請求権(民416、417条)
不法行為責任:(要件)故意・過失、行為の違法性、行為と損害との間の因果関係⇒(効果)損害賠償請求権(民416)、使用者責任(民715)、共同不法行為責任(民719)
問3
(1) 最高裁判所第二小法廷 (2) 昭和56年 (3) 昭和56年6月19日 (4) 原告:X1、X2、被告:Y1、Y2 (5) 被告 (6) 被告
TOPに戻る↑
2.授業評価
登録者:64人 アンケート回答者:25人(39.1%)
全講義回数:20回
* 5:非常にそうである 4:かなりそうである 3:どちらともいえない 2:あまりそうでない 1:全くそうでない
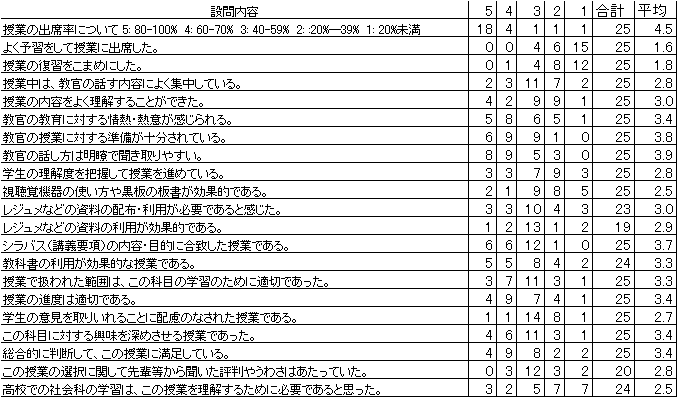
<コメント>* 書式の入力ミスのため、数値に誤りがありましたので、7月11日に修正しました。
登録者中、2度の中間試験の受験者が23人と30人、授業評価のアンケートへの回答者が25人と、出席率が非常に悪いこと、教官の話す内容によく集中しているが2.8点、授業の内容をよく理解することができたが3.0点、教官の教育に対する情熱・熱意が感じられるが3.4点、授業に満足しているが3.4点と、非常に厳しい評価になっています。
自由記載のところでも、「わかりやすくまとめてもらいたかった」「かなり難しかった」「少し難しい」「もう少し板書して欲しい」「表などがあれば、より解りやすかったかもしれない」などの意見がありました。
興味を喚起するために医療過誤を素材としたため、少し難しかったのが影響しているのかもしれません。また、特別に準備した講義であるため、内容をまとめた資料を準備した方が良かったようです。これは反省点です。
また、私の講義にしてはめずらしく「授業の進度をもう少し早くして欲しい」「ダラダラした感じになっている」という意見もありました。授業の進度は適切であるも3.4点しかありません。
できるだけ積極的に授業に参加させ、75分の講義が2コマ連続であるので退屈しないために、さらに、学生の理解度を試し、予習・復習をさせるために、学生に質問したり、当事者の関係図を書かせたりしました。しかし、時間がかかり学生の集中力を奪ってしまって逆効果だったようです。学生の理解度を把握して授業を進めているは2.8点しかありませんでした。予習・復習も、わずかに1.6点と1.8点です。別の工夫が必要なようです。
医療過誤などではなくて、もっと簡単な事例を素材にして、法律の最も基本的な用語などについて講義する方がよかったかもしれません。